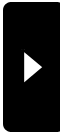2012年05月12日
不動産の広告表示には「築浅」の明確なルールはありません。
不動産業者の「築浅」イメージと、お客様の「築浅」イメージには
少し隔たりがあるように感じます。
このイメージを具体的に数字化したアンケートがありますので
ご紹介致します。
Q.「築浅物件」とは、築何年くらいまでを指すと思いますか?(年単位で記入)
「築浅物件」のイメージは「5 年」までという回答が 45.0%で最も多く、
「5 年までの合計」は 8 割超に及ぶ。
一方で、20 年を超える回答も相当数あり、平均は 5.2 年。
また、男女別では、女性の方が「築浅」を短く考えているようだが、
家族形態別では大きな違いは見られない。

購入・賃貸別では、平均が購入 5.0 年、賃貸 5.5 年と、
購入の方が「築浅」に対してシビア。
また、世帯年収別では、年収が高い方が「築浅」を短く考える傾向にあり、
1,000 万円以上 1,500 万円未満の平均は 4.6 年に。

【不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)調査】
不動産業者の「築浅」イメージと、お客様の「築浅」イメージには
少し隔たりがあるように感じます。
このイメージを具体的に数字化したアンケートがありますので
ご紹介致します。
Q.「築浅物件」とは、築何年くらいまでを指すと思いますか?(年単位で記入)
「築浅物件」のイメージは「5 年」までという回答が 45.0%で最も多く、
「5 年までの合計」は 8 割超に及ぶ。
一方で、20 年を超える回答も相当数あり、平均は 5.2 年。
また、男女別では、女性の方が「築浅」を短く考えているようだが、
家族形態別では大きな違いは見られない。

購入・賃貸別では、平均が購入 5.0 年、賃貸 5.5 年と、
購入の方が「築浅」に対してシビア。
また、世帯年収別では、年収が高い方が「築浅」を短く考える傾向にあり、
1,000 万円以上 1,500 万円未満の平均は 4.6 年に。

【不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)調査】
2012年05月10日
住まいは賃貸と購入のどちらが得なのか…
コラムなどでよく取り上げられる話題ですね。
もちろん、賃料や売買相場が地域で異なりますし、
住宅ローン金利なども変わりますので一概には
「こっちが正解!」とは言えません。
ここに1つの事例をご紹介致します。
住宅購入後、一生の住処と考えずに一定期間で
住み切ってしまうと言う考え方…。
従来の「借り続けるのが得か、買うのが得か」という
議論に別の基軸となる考え方です。
是非、ご参考にされてください。
===============================================================================
【賃貸と住宅購入の中間を求め、
10年で住み切る中古マンションリノベーション】
家族3人の今の暮らしに合わせ、50㎡強の中古マンションをリノベーション。
10年後住替えを視野に入れた、未来と今の可能性を広げる家作り。
家は一生に一度の買い物ではなくなりつつある。
定住よりも、今の暮らしや近い将来のメリットを考え、住宅を購入する人が増えているのだ。
ともに30歳の会社員であるSさんご夫妻は、1歳になる息子さんの誕生を機に引っ越しを考え、
世田谷区内の50㎡程度の部屋を想定し、賃貸と中古マンションの購入を比較検討した。
「中古マンションを購入し、リノベーションして10年後に売却した場合を試算したら、10年家賃を
払い続ける金額と大差がなかった。それなら、自分らしくつくった家に住みたいと思いました」
購入したのは、東急世田谷線の上町駅近くにある築26年、広さ52㎡のマンション。
リノベーションの予算として350万円を準備した。
設計は、以前Sさんが勤めていた設計事務所の同僚だったFさんに相談し、共同設計で
リノベーションを進めた。

2LDKの間取りに仕切られていた壁を全て取り払い、キッチンを中心としたワンルームの空間に変更。
寝室はクイーンサイズのベッドに合わせた最小限の広さとし、新たに間仕切り壁を新設。
その横にウォークインクローゼットもつくった。一方で予算内に収めるために、キッチンや水まわりなど、
生かせるものは既存のまま残している。
「北側には公園があり、光も風も通るので、南側のバルコニーと抜けがつながるプランを提案しました。
さらに、個室の必要性について議論し、10年後に住み替えるなら、そのとき子どもはまだ10歳なので、
ここに住む間は不要ということになり、この案に決まりました」

テレビがある側の壁は、フラットに連続する面を見せ、コンパクトな空間に水平距離の広がりを演出。テレビの配線は壁の中に通した。

「寝室は静かで落ち着いた空間に」というえみさんの希望から、リビングと壁で仕切った。窓側はオープンにして空間をつなげている。
そうして自分たちらしい住まいを手に入れたSさんご家族。
10年後には売却を予定しているが、絶対とは思っていないとSさんは話す。
「賃貸と持ち家の中間のような感覚ですね。今後、仕事や家族の状況に変化があるかもしれないし、
あまり先のことを決めつけず、そのとき次第と考えています」
遠い将来に見通しが利かない時代。
今の暮らしを大切にすると同時に、近い将来にも多くの選択肢と可能性を残すこうした家選びは、
若い世代の共感を呼びそうだ。

キッチンを中心にダイニングとリビングをつなげた一室空間。コンクリートをあらわにした梁が白い空間を切り分けるポイントに。

元個室の壁を取り払い、キッチンと対面させたダイニング空間には自転車を収納するラックも設置。窓からは公園が見える。

既存のキッチンに合わせて、リビングと対面するカウンターを新設。キッチンの奥にはパントリーと小さなテラスがある。
(at home TIME)
コラムなどでよく取り上げられる話題ですね。
もちろん、賃料や売買相場が地域で異なりますし、
住宅ローン金利なども変わりますので一概には
「こっちが正解!」とは言えません。
ここに1つの事例をご紹介致します。
住宅購入後、一生の住処と考えずに一定期間で
住み切ってしまうと言う考え方…。
従来の「借り続けるのが得か、買うのが得か」という
議論に別の基軸となる考え方です。
是非、ご参考にされてください。
===============================================================================
【賃貸と住宅購入の中間を求め、
10年で住み切る中古マンションリノベーション】
家族3人の今の暮らしに合わせ、50㎡強の中古マンションをリノベーション。
10年後住替えを視野に入れた、未来と今の可能性を広げる家作り。
家は一生に一度の買い物ではなくなりつつある。
定住よりも、今の暮らしや近い将来のメリットを考え、住宅を購入する人が増えているのだ。
ともに30歳の会社員であるSさんご夫妻は、1歳になる息子さんの誕生を機に引っ越しを考え、
世田谷区内の50㎡程度の部屋を想定し、賃貸と中古マンションの購入を比較検討した。
「中古マンションを購入し、リノベーションして10年後に売却した場合を試算したら、10年家賃を
払い続ける金額と大差がなかった。それなら、自分らしくつくった家に住みたいと思いました」
購入したのは、東急世田谷線の上町駅近くにある築26年、広さ52㎡のマンション。
リノベーションの予算として350万円を準備した。
設計は、以前Sさんが勤めていた設計事務所の同僚だったFさんに相談し、共同設計で
リノベーションを進めた。

2LDKの間取りに仕切られていた壁を全て取り払い、キッチンを中心としたワンルームの空間に変更。
寝室はクイーンサイズのベッドに合わせた最小限の広さとし、新たに間仕切り壁を新設。
その横にウォークインクローゼットもつくった。一方で予算内に収めるために、キッチンや水まわりなど、
生かせるものは既存のまま残している。
「北側には公園があり、光も風も通るので、南側のバルコニーと抜けがつながるプランを提案しました。
さらに、個室の必要性について議論し、10年後に住み替えるなら、そのとき子どもはまだ10歳なので、
ここに住む間は不要ということになり、この案に決まりました」

テレビがある側の壁は、フラットに連続する面を見せ、コンパクトな空間に水平距離の広がりを演出。テレビの配線は壁の中に通した。

「寝室は静かで落ち着いた空間に」というえみさんの希望から、リビングと壁で仕切った。窓側はオープンにして空間をつなげている。
そうして自分たちらしい住まいを手に入れたSさんご家族。
10年後には売却を予定しているが、絶対とは思っていないとSさんは話す。
「賃貸と持ち家の中間のような感覚ですね。今後、仕事や家族の状況に変化があるかもしれないし、
あまり先のことを決めつけず、そのとき次第と考えています」
遠い将来に見通しが利かない時代。
今の暮らしを大切にすると同時に、近い将来にも多くの選択肢と可能性を残すこうした家選びは、
若い世代の共感を呼びそうだ。

キッチンを中心にダイニングとリビングをつなげた一室空間。コンクリートをあらわにした梁が白い空間を切り分けるポイントに。

元個室の壁を取り払い、キッチンと対面させたダイニング空間には自転車を収納するラックも設置。窓からは公園が見える。

既存のキッチンに合わせて、リビングと対面するカウンターを新設。キッチンの奥にはパントリーと小さなテラスがある。
(at home TIME)
2012年05月07日
【優良中古の認定制度 3段階で評価】
先月頃から少しづつ全容が見えてきた中古住宅の長期優良住宅認定基準案ですが、
今後も注視しなくてはいけません。
ご計画のある方は「知っているだけで得をする」情報もありますのでご注意下さい。
*詳細は弊社までお尋ね下さい
===========================================================
多段階基準に基づき3区分で認定
国土交通省では、3月末に公表した「中古住宅・リフォームトータルプラン」のなかで、
既存住宅における長期優良住宅の認定制度について、2013年度までに認定基準や
評価手法を整備することを盛り込んでおり、以前より技術的調査を進めていました。
今回示された認定基準の検討案では、国民資産の向上、環境負荷の低減、国民負担の
軽減という政策的意義のもと、「有用な(まだ使える)住宅ストックを壊さずに長く
大切に使い続けられる社会としていくこと」が基本コンセプトとして位置付けられました。
違反建築物を除くすべての既存住宅ストックを対象に、既存住宅の状態および改修後の
状態を認定基準に基づき評価するとしています。
認定基準は、①劣化対策、②耐震性、③維持管理・更新容易性、④省エネルギー対策を
基本4項目とし、新築制度における項目のほか、避難安全性、室内空気環境、設備の適法性
などの既存特有の項目が追加されました。
基本4項目については建設時期による住宅性能の違いを考慮して基準を多段階に設定し、
それ以外の項目と合わせて総合的に評価することで、3区分の認定を行うとしています。
認定区分は
新築の認定基準と同水準の住宅を「S」
既存住宅として一定の優良性・長期性を有する住宅を「A」
一部の項目について優良な性能を有する住宅を「B」
とし、「S」評価の住宅には新築制度と同等のインセンティブを与えるとしています。
木造住宅の認定基準案も
基本4項目の認定基準案も示されました。木造一戸建住宅について、
①劣化対策では、住宅性能表示制度の劣化対策等級をベースに床下・小屋裏点検口、
浴室・洗面所の防水措置などを加味して評価する
②耐震性については、昭和56年以前と以降の住宅に分け、以前は耐震改修促進法の
構造耐震指標を、以降は耐震等級をもとに評価する
③維持管理・更新容易性では、配管の清掃、点検、補修の容易性を状況に応じて評価する
④省エネルギー対策では、平成11年基準(次世代省エネルギー基準)をもとに評価する
などの方向が示されています。
新築は約3割が長期優良住宅に
同省は4月13日、新築における長期優良住宅について、2011年度の認定状況を公表しました。
認定戸数は一戸建住宅が10万2,767戸、共同住宅が2,738戸で、合計10万5,505戸となって
います。新設住宅着工戸数と比較すると、持ち家の約3割が長期優良住宅の認定を取得して
いることになります。
長期優良住宅の認定制度開始より3年が経過するなか、制度が定着するとともに、
エンドユーザーへの周知も進んできています。
今後、既存住宅においても認定制度が整備されることで、中古住宅流通・リフォーム市場の
さらなる拡大が期待されます。
(株式会社ナイス)
===========================================================
(住宅新報)

2012年05月02日

マイホーム購入の相談に応じていると、希望に沿った住まいが目の前にあるにもかかわらず、
購入を決断できないケースにしばしば遭遇します。
住宅は個別性が高く、人気の住宅は足が速いだけに、タイミングを逸すると同条件の住宅に
巡り合うのはなかなか難しい、ということも少なくありません。
わかっているのになぜ購入に踏み切れないのでしょうか。
二つの理由が考えられます。
一つは、マイホーム購入の目的が明確でないこと。
もう一つは、自分の購入予算が明確でないこと。
今回は購入目的について考えていきます。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■納得のマイホーム購入のために、明確にしたいこと
一生に一度あるかないかの大きな買い物であるマイホーム購入。
だからこそ、自分や家族にあった住宅を無理のない予算で購入したい、
誰もがそう考えるのではないでしょうか。
自分たちにぴったりの住宅を見極めるためには、以下の三つを明確にしなければなりません。
1、マイホーム購入の目的
2、マイホームの必要時期
3、マイホームに対する希望条件
要は、何のためにマイホームが必要なのか(目的)、いつ引っ越したいのか(必要時期)、
どのような条件を住宅に望むのか(希望条件)。これら3ポイントを明確にすることが重要です。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■マイホーム購入の目的は何ですか?
あなたは、何のためにマイホームを購入するのでしょうか。
「家賃がもったいない」「今の家が古くて心配」「もっと駅から近くて便利な場所に住みたい」
「子どもが大きくなって手狭になった」など、それぞれの事情があるに違いありません。
マイホーム購入の動機や目的は、現在の住宅に対する不満や不安から発生している
ケースが多く、新居を選ぶ際はその不満や不安が解消される住宅でなければ納得も
満足もできません。
「何のためのマイホーム購入か」を明確にすることは、自分や家族にぴったりの住宅を
選ぶための必要最低限の事前準備です。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■マイホームはいつ必要?
住宅は、売買契約後すぐに入居できるものもあれば、建築中で来春にならないと
引っ越しできないなど、すぐに住めないものがあります。
入居希望時期と入居可能日を合わせることが大切です。
「結婚を機に」「子どもの進学までに」など、購入時期が限定されている場合は特に、
購入する住宅の入居可能日を合わせておかなければ、その間の仮住まいの賃料など
もったいないケースが出てくるため要注意です。
-------------------------------------------------------------------------------------------
■どのような住宅に住みたいですか?
希望の場所、希望の住宅、希望の資金計画はありますか。
場当たり的に住まい探しを行うのは非効率です。限られた時間を有効に使い、
できる限り広範囲で探すには、事前準備がポイントです。
ここでの事前準備とは、希望条件をすべてピックアップし、優先順位をつけることです。
マイホーム探しの指針となる、自分と家族の希望条件を明確にしておきます。
マイホーム購入を検討し始めたらすぐに、エリアや沿線・最寄り駅、住宅の広さや間取り、
設備仕様、資金プラン・返済プランなど、購入にあたっての「ああしたい、こうしたい」
「あれが欲しい、これが欲しい」をすべてピックアップしてください。
購入の検討が進めば進むほど、当初の自分の思い、家族の希望などのよりどころへ
立ち戻る必要が出てきます。これは特に、A住宅にしようか、B住宅にしようか、と
絞り込みの際に威力を発揮します。
希望条件とその優先順位が明確であれば、より自分と家族にぴったりの住宅を選ぶ
ことが可能です。
納得のマイホーム選びに向けてぜひ、「何のために」「いつ」「どのような」の三つのポイントを
明確にして臨んでください。
(at home不動産抜粋)
2012年04月24日

むやみに不安を煽ることはいけませんが…これはちょっとショックな数字です。
耐震診断を実施した全国の木造住宅のうち、90.32%が震度6強クラスの地震で
倒壊の恐れがあることが発表されました。
以下、記事です。
=================================================================
住宅リフォーム業者などでつくる日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)が
2006年4月~11年11月に耐震診断を実施した全国の木造住宅のうち、90.32%が
震度6強クラスの地震で倒壊の恐れがあることが19日までに分かった。
首都直下地震の被害想定が見直された東京都も、診断対象1859棟のうち92.74%が
倒壊の恐れがあった。
都防災会議の新しい被害想定では、東京湾北部が震源のマグニチュード(M)7.3の場合、
震度6強以上の範囲は23区の約7割に達し、建物全壊は約11万6千棟、それによる死者は
最大約7千人。木耐協は「まずは現状を知り、万一に備えてほしい」としている。
木耐協は、全国で診断依頼があった建物1万3674棟を建物の構造、壁の量などから
「倒壊しない」「一応倒壊しない」「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」の
4段階で評価。
その結果、「倒壊しない」は1.46%、「一応倒壊しない」は8.23%にとどまった。
一方、「倒壊する可能性がある」は19.48%で、「倒壊する可能性が高い」が
最多の70.84%に達した。
また建築基準法に定めた耐震基準が強化された1981年以降の建物も、約8割が
「倒壊の可能性がある」か「可能性が高い」との結果。
木耐協は「経年劣化などにより、新耐震基準でも単純に安心とはいえない」としている。
(日経2012.04.20)
=================================================================
ここで、大分県の調査結果を抜粋しましたのでご覧下さい。


http://www.mokutaikyo.com/data/20120420.pdf
調査対象は70戸で、評点1.0(耐震改修工事で確保する評点は1.0以上です)未満の
戸数は58戸で約83%に上ります。
全国値よりは若干いいですが、かなり深刻な数字と思いませんか?
その他の工法の家でも、築年数に応じて耐震性が不足していると推察されます。
大きな地震の際には、最低限命が守れる住宅でありたいものです。
昨今は耐震診断や耐震改修工事に補助も出て行政のインセンティブもあります。
これを機にご一考いただければ嬉しい限りです。
2012年04月22日
【40歳未満の45.6%が1000万円超の高額リフォームを一戸建住宅で実施】
一戸建て住宅リフォーム費用「1,000万円超」、40歳未満で45.6%、70歳以上では13.5%
一戸建て住宅におけるリフォーム(1,080件)の場合、リフォーム契約金額を見ると、40歳未満では
「1,000万円超」が45.6%と最も高い割合を占めているのに対し、40代では27.1%、50代では20.9%、
60代では14.9%、70歳以上では13.5%と、割合は低くなっている(図1)。
40歳未満の住宅の取得方法は、「注文住宅(建て替え含む)」と「親からの相続等」でそれぞれ
33.3%を占め、次いで「中古住宅購入」(22.2%)の順だった。
世帯や嗜好に対応させるため、借り入れも使いながら大規模なリフォームを実施している一方で、
50・60代は老朽化対応を中心としたリフォーム、70歳以上は金額を抑えた高齢化対応リフォームを
行っていると見える。
マンションにおけるリフォーム(81件)の場合では、500万円超の高額なリフォームは50代が最も多い(図2)。
また、50代は、築20~25年以下(25.0%)、築25~30年以下(18.8%)、築30年超(18.8%)など、築年数の
経過した古いマンションでリフォームを行っている。


※(一社)住宅リフォーム推進協議会 「平成23年度 住宅リフォーム実例調査」
40歳未満は「住宅ローン減税」、70歳以上は「地方自治体の補助」を多く利用
一戸建て住宅の場合で、住宅リフォーム支援策の活用状況を年齢別に見てみると、リフォーム資金のうち
借入金が高くなる40歳未満では、住宅ローン減税を利用した割合が20.0%と最も高い。
一方、70歳以上では、地方自治体の住宅リフォームに関する補助を利用した割合が12.8%と最も高くなって
いる。住宅リフォーム支援策の検討においては世代による利用の傾向にも着目する必要がある。
また、平成21年度の調査と比べると、省エネリフォーム工事の件数が8,772件から1万3,843件と、
約1.6倍に増加。
特に、住宅エコポイント制度を利用した割合が46.2%(一戸建て住宅48.0%、マンション23.2%)と
半数近くに達した点が注目される。
住宅エコポイントが窓の省エネ改修によく利用されており、窓ガラス・サッシの改良等のリフォーム工事が
増加している。
(一社)住宅リフォーム推進協議会
2012年04月19日

【リフォームの潜在需要は約65% 中古マンションを購入してのリフォームが増加傾向に】
若年層を中心に中古マンションを購入してリフォームする人が増加
「住宅リフォーム実例調査」8回目結果。
リフォームした住宅の当初の取得方法としては、「中古住宅購入」が増加傾向にある。特に、マンションでは、
平成22年度で「新築分譲住宅購入」を初めて上回り、45.1%となった(図1)。
中古マンションを購入してリフォームを行う傾向は、若年層に多く見られ、年代別に見ると、40歳未満(18件)が
66.7%、40代(34件)が67.6%、50代(30件)が30.0%、60歳以上(51件)が31.4%。
特に40代以下の世代では、約3分の2と非常に高くなっている。
また、リフォームした住宅を築年別に見ると、一戸建てでは築25年以上が43.1%(「25~30年以下」20.7%、
「30年超」22.4%)で、マンションでは39.9%(「25~30年以下」22.6%、「30年超」17.3%)となり、「比較的
新しい住宅のリフォーム事例が多かった」マンションでも築年の古い住宅が増えている。
同協議会では、「1970年代後半から1980年代に建設されたマンションの大量ストックがあり、今後さらに
この年代のマンションでのリフォーム需要の増加が見込まれる」と見ている。
図1:当初の住宅の取得方法 年度別(マンション)

※(社)住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォーム実例調査」
リフォームの潜在需要は約65%、最も不安に感じるのは「見積もりの相場・適正価格」
調査によると、リフォームをしたいと思っている層は、時期が未定の潜在層を含めると64.7%だった。このうち、
10年以内にリフォーム意向がある顕在層は、19.4%と約2割。この傾向は「戸建て層、マンション層いずれに
おいても、同様に見られる」という。
今回の調査で新たに追加した「リフォームを行う際の不安や心配事」について見ると、本調査において、
リフォームを検討している人が不安を感じる点で最も多かったのは、
「見積もりの相場や適正価格がわからない」(全体50.8%、一戸建て51.1%、マンション49.8%)だった(図2)。
次いで「施工が適正に行われるか」(同39.4%、39.1%、40.7%)、「費用がかかる」(同29.5%、31.1%、
24.1%)となり、「『価格に対する不安』、『適正な施工・対応への心配』の大きさがうかがえる結果」となった。
図2:不安を感じる点

また、情報不足を感じる点では、「リフォームにかかる費用の目安や積算の基準」(同67.3%、67.3%、67.6%)
が最も多く、6割を超えている(図3)。次いで、「工事の依頼先選びの目安や基準(信頼できる事業者選びに
関する情報)」(同30.4%、29.2%、34.9%)、「自分のイメージに近い具体的なリフォーム事例の情報」
(同23.2%、22.6%、25.3%)となった。
図3:情報不足を感じる点

※(社)住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査」
2012年04月17日
【上階の騒音に慰謝料60万円! こんなことにならないためには?】
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)