
2012年09月28日

前回同様に、不動産売買の場面で買主様より「瑕疵担保」について
ご質問が有りましたのでここに纏めておきます。
「瑕疵担保」については少し解釈が難しいかも知れませんが、売主様や
買主様は勿論、我々業者も大変に重要な事項です。
宜しければご覧下さい。
「瑕疵」
「きず」「不具合」「欠陥」という意味
「隠れたる瑕疵」
特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、
買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を
働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のこと
「瑕疵担保責任」
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、
売主が負うべき責任
買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、
または契約を解除することができる
*宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するとき、買主が瑕疵担保
責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる
仲介業者の注意義務違反と売主の責任は?
Q 本当に「隠れて」いて、仲介業者も気が付かないような瑕疵については、
誰が責任を負うことになるのですか。
A 当然、「売主」が負うということになります。これが民法570条の趣旨です。
つまり、売主の瑕疵担保責任は「無過失責任」ということです。
しかし、本当に誰もが気が付かないような瑕疵のある場合は、瑕疵の発見までに
何年も掛かるということが考えられます。このような場合には、判例で、瑕疵担保責任に
基づく損害賠償請求権は一般の債権と同じであるからという理由で、10年の消滅時効に
掛かるとされています。
つまり、瑕疵の発見までに10年が経過すれば、事実上、売主に対し瑕疵担保責任を
追及できないということです。ただ、例えば売主が意図的に、あるいは過失で建物を
解体したときのコンクリート片や残材などを地中に埋め込んでしまったというような
場合には、同じ「隠れた瑕疵」でも、売主の不法行為として、不法行為の時から20年間
責任追及できる可能性があります。
Q そうすると、プロでもなかなか発見しにくいような瑕疵の場合には、売主の瑕疵担保責任なり
不法行為責任を追及するということになるが、仲介業者が通常の注意をすれば発見できるような
瑕疵であれば、仲介業者だけの責任ということになるのですか。
A そうではありません。前者の場合には、売主の瑕疵担保責任や不法行為責任ということでよいと
思いますが、後者の場合には、仲介業者だけの責任ということではなく、売主と仲介業者との
共同責任となります。
そして、この場合の責任は、判例で、両者は不真正連帯債務の関係に立ち、それぞれが
買主に対し、その損害の全額について責任を負うとされています。
Q ということは、売主も全額、仲介業者も全額責任を負うということですから、もし仲介業者が
全額責任を負った場合、その半分は売主に請求できますか。
A 売主と仲介業者との間には「負担部分」というものがありませんので、判例は当然には請求
できるとはしていませんが、そのような場合には、売主の「不当利得」ということが考えられ
ますので、両者の責任の度合に応じて、応分の請求はできると思います。
2012年09月24日

中古住宅の売買において、付帯設備(住宅設備や門扉、照明器具等)の責任の所在について
お客様より質問を受けました。お引き渡しのあった物件に付帯している設備の瑕疵担保責任に
ついて詳しく書いておりますのでご参考にされて下さい。
瑕疵担保責任は中古の付帯設備についても及ぶか?
Q 瑕疵担保責任は、中古の付帯設備についてもその責任が及ぶのでしょうか。
A 及びます。なぜならば、その付帯設備も売買の対象になっているからです。
Q そうなると、新築物件の場合はあまり問題ないと思いますが、中古物件の場合には
設備そのものが古くなっていますので、どうしても故障しがちになると思います。
それでも、瑕疵担保責任を負わなければならないのでしょうか。
A そのようなことはありません。要は、その設備が売買契約の締結時に故障していなければ、
その設備は正常に作動しているわけですから、その設備に「隠れた瑕疵」があるということには
なりません。したがって、仮にその設備が引き渡し後1か月で故障したとしても、売主がその故障に
対し瑕疵担保責任を負うということはありません。なぜならば、瑕疵担保責任が発生するための
要件である「売買契約の締結時」に「隠れた瑕疵」があったわけではないからです。
ただ、その設備がほこりだらけであったり、標準的な耐用年数内にあるにもかかわらず、過去に
たびたび故障していたというような事情でもあれば、売主の告知義務違反ということが考えられますが、
それでも、必ずしも売主に瑕疵担保責任が発生するということではありません。
そして仲介業者においても、事前の物件調査の段階で、現に故障なく正常に作動していることを確認し、
その旨を買主に付帯物表等で説明していれば、仮に過去の故障の事実を売主から説明を受けていなくても
(売主が本当のことを言わないことが多い)、仲介業者が注意義務違反(説明義務違反)に問われることは
ないと思います。
Q ということは、仲介業者が付帯設備の調査をし、「契約時」に正常に作動していることを買主に告知
していれば、売主が瑕疵担保責任に問われることはなく、仲介業者も注意義務違反に問われることは
ないと考えてよいということですね。
A その通りです。中古の付帯設備は、最近修理をしたとかというような特別な事情がない限り、
経年劣化により、いつ故障してもやむを得ないと考えられるからです。
(住宅新報web 不動産取引現場での意外な誤解 売買編より)
2012年09月19日
先日、弊社受託物件をお客さまにご見学していただきました。
お待ち合わせ時間の少し前に物件に到着し、室内の換気を
するために窓を開けていきます。2階の窓を開けていると、
お隣の敷地に植えられている栗の木が目に飛び込んできました。

最近は朝晩が涼しくなり始めてきましたが、こんなところにも
秋の気配が…。
しかし、結構な大きさに育っている栗の木は、当該地敷地の
境界に迫っています。このまま栗の実が育ち、地面に落ちると
こちらの敷地に転がり込んでくるのは確実です。
というか、すでに敷地内に落ちています。(笑)
これ…頂いてもいいですかね??
物件概要の設備欄に「秋は栗がたくさん食べられます」と
記載したくなります。(*^_^*)
2012年09月05日

本日の日経に、13年度から住宅ローン「フラット35」で若年層向けに金利引下げ
0.5%の優遇措置が行われる旨の記事がありました。
建物の性能が一定基準以上の場合に限る「フラット35S」と利用する際に35歳以下を
対象としているようです。
優遇措置部分の上限金額が2000万円らしいので、借入総額と返済年数次第では
総支払額の差が100万円を超える…かな?
詳細は注視しておかねばなりませんが、またまた消費者様には嬉しいニュースですね。
【若年層向け住宅ローン優遇 フラット35で0.5% 13年度から、国交省検討】
国土交通省は主に若年層の住宅購入を後押しするため、2013年度から住宅金融支援機構が
取り扱う長期固定金利型の住宅ローン「フラット35S」の新しい金利優遇制度を設ける方針だ。
初めて一戸建てや分譲マンションを購入する人を対象に、通常は0.3%の金利優遇幅を0.5%
にする。先行きに不透明感が漂う国内の住宅投資を下支えする狙いがある。
フラット35Sは最長35年の長期固定金利の住宅ローンで、機構が民間金融機関から住宅ローン
債権を買いとり、証券化して機関投資家に売却して資金を調達する。住宅ローンの新規融資全体
のうち2割程度のシェアを占める。
フラット35全体の融資実績はサービスを始めた03年から累計で約11兆円にのぼる。
国交省は来年度予算案の概算要求で、当初10年間はフラット35Sの金利を0.5%引き下げるよう
求める。0.5%優遇の対象となる貸出額の上限は2千万円。今の金利水準なら新制度を利用する
人は当初10年間、年1%台前半と民間の年2~3%より大幅に安く長期固定金利の住宅ローンを
借りられる。
新制度は貸出金利を優遇することで、35歳以下の若年層や中低所得者がマンションなどを購入
しやすくするのが狙い。欧米に比べて取引が低迷している中古住宅市場を活性化させる効果も
見込まれている。優遇する貸出額に上限を設けることで、新築より安価な中古住宅の購入を促す
効果が期待できるためだ。
新たな優遇策は国民新党などが求めていた。来年度の予算要求額は170億円程度の見込みだ。
政府は10年2月から経済対策でフラット35Sの金利を当初10年間は1%優遇する制度を始めた。
11年9月に期限が切れたが、昨年12月から復活して当初5年間は0.7%を優遇している。
ただこの優遇措置も今年10月に期限が切れる予定になっている。
(2012.09.05 日経web)
2012年09月04日
二世帯同居のメリットは「相互の助け合い・交流」「万が一の時の安心」
インターネット調査(総数1,000人)で二世帯同居のメリットを聞いたところ、上位3項目は、
親世帯では「生活面で相互に助け合える」「孫の成長を間近に見る楽しみ」「万が一の時の安心」、
子世帯では「親の健康状態をすぐに把握できる」「育児の日常的サポート」「万が一の時に安心」
となった。
また、子世帯では「日常の生活費を少なくできる」「自分や家族の体調不良時のサポート」「家事の
日常的サポート」も、上位3項目と同程度に多く挙げられていることから、同社では、「親世帯・子世帯
ともに、相互の助け合いや万が一の場合の安心をメリットとして感じて」おり、特に「子世帯は親世帯
からの家事・育児の日常的サポートや、生活費や住宅購入費が抑えられるなどの経済的なメリットを
感じている」と見ている。
一方、デメリットについては、親世帯より子世帯のほうがデメリットを感じる割合が高い。
子世帯では「世帯間の価値観の違いによるストレス」「気が休まらない・気疲れ」「友人を家に呼びづらい」
が上位に挙げられている。
さらに同社は、デメリットを感じる割合は「特に、嫁姑の関係がある息子同居の妻においては顕著に高い」
と見ている。ただし、自分の親と同居する娘同居の妻では、「親世帯の干渉によるストレス」や「配偶者
への気遣いのストレス」が、他の同居スタイルよりも突出して高かった。
二世帯同居に対する満足度を聞いたところ、親世帯は子世帯よりも総じて満足度が高い結果となった(図1)。
特に、息子同居・娘同居の場合ともに、母親の満足度が高くなっている。
【図1:同居スタイル別に見た二世帯同居に対する満足度(総数1,000人)】
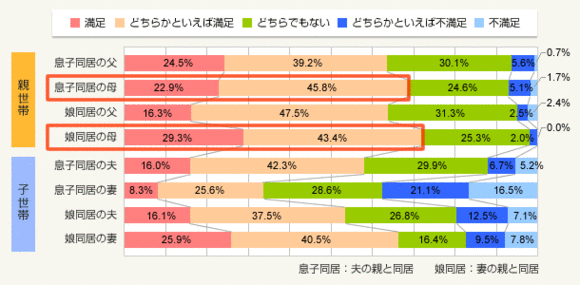
二世帯の関係が良好な空間・ストレスに感じる空間は、ともにリビング、玄関が上位に
郵送調査(総数121世帯)で、二世帯の関係が良好な空間とその理由を聞いたところ、
最も多かったのはリビング(19.6%)で、次いで玄関(12.5%)、ダイニング(9.6%)の順(図2)。
多かった理由としては、リビングでは「二世帯の交流ができる」「孫と交流ができる」、玄関では
「収納が充実している」「世帯別に空間を設けた」、ダイニングでは「二世帯の交流ができる」となった。
一方、ストレスを感じる空間とその理由を聞いたところ、最も多かったのは玄関(18.6%)で、次いで
リビング(10.5%)、浴室(8.9%)の順となっている。多かった理由は、玄関では「収納量が不足
している」「世帯別に空間を設けたかった」、リビングでは「収納量が不足している」、浴室では
「世帯別に空間を設けたかった」「入浴時の音が気になる」だった。
同社は、「関係が良好な理由、ストレスに感じる理由のどちらにも『収納』が挙がっており、収納問題
の解決は二世帯の住まいの快適性に大きく左右すると考えられる」と分析している。
さらに、二世帯同居における収納について聞いたところ、二世帯同居が原因で収納について
困っている空間は、玄関が59.3%と6割近くを占め、次いで洗面脱衣室(32.6%)、キッチン(24.4%)、
リビング(23.3%)、子ども部屋(22.1%)、和室(20.9%)、主寝室(18.6%)の順となった。
具体的な困りごとは、玄関では「二世帯分の収納量が足りない」(70.3%)、「片方の世帯が場所を
とり過ぎる」(23.4%)、「世帯間で使用範囲があいまい」(17.2%)、洗面脱衣室では「二世帯分の
収納量が足りない」(36.4%)、「両世帯のものが混在している」(20.5%)、「世帯間で使用範囲が
あいまい」(18.2%)、リビングでは「子どもや孫のもので散らかる、片付かない」(40.6%)、
「二世帯分の収納量が足りない」(28.1%)、「世帯間で使用範囲があいまい」(21.9%)が
挙げられている。
【図2:二世帯の関係が良好な空間・ストレスを感じている空間(総数121件)】
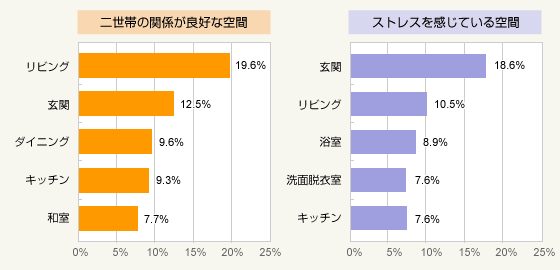
※パナホーム(株) 「二世帯住宅に関する生活者調査」より

