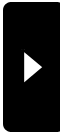2012年04月24日

むやみに不安を煽ることはいけませんが…これはちょっとショックな数字です。
耐震診断を実施した全国の木造住宅のうち、90.32%が震度6強クラスの地震で
倒壊の恐れがあることが発表されました。
以下、記事です。
=================================================================
住宅リフォーム業者などでつくる日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)が
2006年4月~11年11月に耐震診断を実施した全国の木造住宅のうち、90.32%が
震度6強クラスの地震で倒壊の恐れがあることが19日までに分かった。
首都直下地震の被害想定が見直された東京都も、診断対象1859棟のうち92.74%が
倒壊の恐れがあった。
都防災会議の新しい被害想定では、東京湾北部が震源のマグニチュード(M)7.3の場合、
震度6強以上の範囲は23区の約7割に達し、建物全壊は約11万6千棟、それによる死者は
最大約7千人。木耐協は「まずは現状を知り、万一に備えてほしい」としている。
木耐協は、全国で診断依頼があった建物1万3674棟を建物の構造、壁の量などから
「倒壊しない」「一応倒壊しない」「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」の
4段階で評価。
その結果、「倒壊しない」は1.46%、「一応倒壊しない」は8.23%にとどまった。
一方、「倒壊する可能性がある」は19.48%で、「倒壊する可能性が高い」が
最多の70.84%に達した。
また建築基準法に定めた耐震基準が強化された1981年以降の建物も、約8割が
「倒壊の可能性がある」か「可能性が高い」との結果。
木耐協は「経年劣化などにより、新耐震基準でも単純に安心とはいえない」としている。
(日経2012.04.20)
=================================================================
ここで、大分県の調査結果を抜粋しましたのでご覧下さい。


http://www.mokutaikyo.com/data/20120420.pdf
調査対象は70戸で、評点1.0(耐震改修工事で確保する評点は1.0以上です)未満の
戸数は58戸で約83%に上ります。
全国値よりは若干いいですが、かなり深刻な数字と思いませんか?
その他の工法の家でも、築年数に応じて耐震性が不足していると推察されます。
大きな地震の際には、最低限命が守れる住宅でありたいものです。
昨今は耐震診断や耐震改修工事に補助も出て行政のインセンティブもあります。
これを機にご一考いただければ嬉しい限りです。
2012年04月22日
【40歳未満の45.6%が1000万円超の高額リフォームを一戸建住宅で実施】
一戸建て住宅リフォーム費用「1,000万円超」、40歳未満で45.6%、70歳以上では13.5%
一戸建て住宅におけるリフォーム(1,080件)の場合、リフォーム契約金額を見ると、40歳未満では
「1,000万円超」が45.6%と最も高い割合を占めているのに対し、40代では27.1%、50代では20.9%、
60代では14.9%、70歳以上では13.5%と、割合は低くなっている(図1)。
40歳未満の住宅の取得方法は、「注文住宅(建て替え含む)」と「親からの相続等」でそれぞれ
33.3%を占め、次いで「中古住宅購入」(22.2%)の順だった。
世帯や嗜好に対応させるため、借り入れも使いながら大規模なリフォームを実施している一方で、
50・60代は老朽化対応を中心としたリフォーム、70歳以上は金額を抑えた高齢化対応リフォームを
行っていると見える。
マンションにおけるリフォーム(81件)の場合では、500万円超の高額なリフォームは50代が最も多い(図2)。
また、50代は、築20~25年以下(25.0%)、築25~30年以下(18.8%)、築30年超(18.8%)など、築年数の
経過した古いマンションでリフォームを行っている。


※(一社)住宅リフォーム推進協議会 「平成23年度 住宅リフォーム実例調査」
40歳未満は「住宅ローン減税」、70歳以上は「地方自治体の補助」を多く利用
一戸建て住宅の場合で、住宅リフォーム支援策の活用状況を年齢別に見てみると、リフォーム資金のうち
借入金が高くなる40歳未満では、住宅ローン減税を利用した割合が20.0%と最も高い。
一方、70歳以上では、地方自治体の住宅リフォームに関する補助を利用した割合が12.8%と最も高くなって
いる。住宅リフォーム支援策の検討においては世代による利用の傾向にも着目する必要がある。
また、平成21年度の調査と比べると、省エネリフォーム工事の件数が8,772件から1万3,843件と、
約1.6倍に増加。
特に、住宅エコポイント制度を利用した割合が46.2%(一戸建て住宅48.0%、マンション23.2%)と
半数近くに達した点が注目される。
住宅エコポイントが窓の省エネ改修によく利用されており、窓ガラス・サッシの改良等のリフォーム工事が
増加している。
(一社)住宅リフォーム推進協議会
2012年04月19日

【リフォームの潜在需要は約65% 中古マンションを購入してのリフォームが増加傾向に】
若年層を中心に中古マンションを購入してリフォームする人が増加
「住宅リフォーム実例調査」8回目結果。
リフォームした住宅の当初の取得方法としては、「中古住宅購入」が増加傾向にある。特に、マンションでは、
平成22年度で「新築分譲住宅購入」を初めて上回り、45.1%となった(図1)。
中古マンションを購入してリフォームを行う傾向は、若年層に多く見られ、年代別に見ると、40歳未満(18件)が
66.7%、40代(34件)が67.6%、50代(30件)が30.0%、60歳以上(51件)が31.4%。
特に40代以下の世代では、約3分の2と非常に高くなっている。
また、リフォームした住宅を築年別に見ると、一戸建てでは築25年以上が43.1%(「25~30年以下」20.7%、
「30年超」22.4%)で、マンションでは39.9%(「25~30年以下」22.6%、「30年超」17.3%)となり、「比較的
新しい住宅のリフォーム事例が多かった」マンションでも築年の古い住宅が増えている。
同協議会では、「1970年代後半から1980年代に建設されたマンションの大量ストックがあり、今後さらに
この年代のマンションでのリフォーム需要の増加が見込まれる」と見ている。
図1:当初の住宅の取得方法 年度別(マンション)

※(社)住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォーム実例調査」
リフォームの潜在需要は約65%、最も不安に感じるのは「見積もりの相場・適正価格」
調査によると、リフォームをしたいと思っている層は、時期が未定の潜在層を含めると64.7%だった。このうち、
10年以内にリフォーム意向がある顕在層は、19.4%と約2割。この傾向は「戸建て層、マンション層いずれに
おいても、同様に見られる」という。
今回の調査で新たに追加した「リフォームを行う際の不安や心配事」について見ると、本調査において、
リフォームを検討している人が不安を感じる点で最も多かったのは、
「見積もりの相場や適正価格がわからない」(全体50.8%、一戸建て51.1%、マンション49.8%)だった(図2)。
次いで「施工が適正に行われるか」(同39.4%、39.1%、40.7%)、「費用がかかる」(同29.5%、31.1%、
24.1%)となり、「『価格に対する不安』、『適正な施工・対応への心配』の大きさがうかがえる結果」となった。
図2:不安を感じる点

また、情報不足を感じる点では、「リフォームにかかる費用の目安や積算の基準」(同67.3%、67.3%、67.6%)
が最も多く、6割を超えている(図3)。次いで、「工事の依頼先選びの目安や基準(信頼できる事業者選びに
関する情報)」(同30.4%、29.2%、34.9%)、「自分のイメージに近い具体的なリフォーム事例の情報」
(同23.2%、22.6%、25.3%)となった。
図3:情報不足を感じる点

※(社)住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査」
2012年04月17日
【上階の騒音に慰謝料60万円! こんなことにならないためには?】
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)
2012年04月17日
2012年04月08日
中古売マンション物件のご紹介です。
【大分市荏隈 中古売マンション】

詳しくはコチラ >>>
4LDK 1250万円
日当り良好、角部屋物件です!
平成24年3月内装リフォーム 、1階のお部屋で専用庭があります。
【大分市荏隈 中古売マンション】

詳しくはコチラ >>>
4LDK 1250万円
日当り良好、角部屋物件です!
平成24年3月内装リフォーム 、1階のお部屋で専用庭があります。