
2012年06月04日
■マンションの寿命は30年?
「日本の住宅は欧米に比べて寿命が短い」とよく言われます。
マンションの購入希望者の中にも、同じようなイメージを持っている人は少なくありません。
その根拠の一つに挙げられるのが図1のデータです。
日本の住宅は30年、アメリカが55年、イギリスが77年・・・。
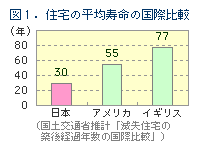
これを見て「マンションは30年しかもたない」と思ってしまう人もいるようです。
しかし、それは正しくありません。この図の基になったデータは「滅失住宅の築後経過年数」です。
理由のいかんを問わず、取り壊された時点の築年数を単純に平均した数値を示しています。
災害で損壊を受けて取り壊された例もあれば、まだまだ使える住宅を新たに建て替えるために
解体した例もあるでしょう。
しかも、このデータはマンションだけでなく木造一戸建ても含めた住宅全体の統計です。
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造や鉄筋コンクリート(RC)造のマンションの寿命が30年しかない・・・
というわけではないのです。
■40年以内に建て替えられるマンションも!その理由は?
では、マンションは何年くらいで建て替えられているのでしょうか。
1970年代半ばから現在までの30数年間で建て替えられた事例は、100件程度しかありません(阪神淡路
大震災の再建マンションは除く)。その建て替え時の築年数を見ると40年未満のマンションもあります。
「40年」という数字だけで判断すれば、確かに短いですね。
しかし、建て替えの理由を見ると、コンクリートが朽ち果てて物理的な寿命が来たというケースではないようです。
その多くは、骨組みはしっかりしていても設備配管類が老朽化して修繕や交換にコストがかかり過ぎる
といった経済的理由や、5階建てでエレベーターがないなど、
現代の生活実態に合わないといった機能的理由が中心です。
また、1970年代頃までにできたマンションは、容積率が余っているケースが少なくありません。
これまで建て替えに成功したのは、法定容積率に満たない余った容積を生かし、床面積を増やして
土地の高度利用を図ったケースがほとんどです。
容積率いっぱいに建てられている場合でも、複数のマンションやビルの再開発などによって容積の緩和を
受けて建て替えを実現したケースもあります。1990年前後のバブル期には、わずか築20年程度で建て替え
られた事例がありました。地価暴騰で容積を余らせておくのがもったいないとか、小さいビルをまとめて大きく
したほうが付加価値が上がるから再開発するなど、社会的背景が引き金になった例も多いのです。
その意味で、単純に「建て替え時の築年数=寿命」とは、考えないほうが賢明でしょう。
■法定耐用年数が一つの目安
「マンションの寿命は何年?」という質問には、「実際のところはわからない」というのが、
現状を踏まえた答えといわざるをえません。
というのも、日本にマンションができ始めてから50年足らずの歴史しかなく、物理的に朽ち果てて
寿命を迎えた事例がまだないからです。
しかし、「わからない」中でも一つの目安になるのが法定耐用年数です。
これは、会計上の減価償却費を計算するために財務省令で定められたもので、資産の種類、構造、
用途によって異なります。鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造や鉄筋コンクリート(RC)造の建物の
耐用年数は、1998年以降に建てられたものは住宅で47年、事務所で50年となります(「SRC造やRC造の
住宅=マンション」と考えてください)。
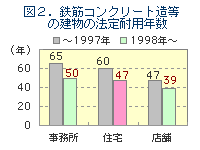
ただし、あくまでも「耐用年数=寿命」とは言えないことに注意してください。
法定耐用年数は「標準的な資産を対象とし、原則として、通常の維持補修を加えながら通常の
使用条件で使用した場合の効用持続年数を基礎として定める」と定義されています。
会計上の基準ですから、物理的な側面よりも「効用」、つまり経済的・機能的な価値に基づいているのです。
時代によっても変化します。現在の法定耐用年数は1998年に改定されました。
住宅の場合、現行で47年ですが、改定前は60年と、約2割短縮したわけです。
もちろん、物理的な寿命が短くなったわけではありません。前述した機能的、社会的な要素が強いと考えられます。
むしろ、素材の質が向上し、建設技術も進んでいるため、物理的な寿命は現在のほうが伸びているはずです。
昨今の「200年住宅」を目指す動きも、こうした技術的背景が裏付けになっています。
■マンションの寿命は居住者が作るもの
マンションの寿命は人間の寿命に似ています。日本人の平均寿命は、男性が79歳、女性が86歳
(2007年・厚生労働省発表データより)ですが、誰もが同じようにその年まで生きるわけではありません。
天寿もあるかもしれませんが、健康管理を心がけることで長生きできるようになります。
マンションにおいても、建物の保守点検をきちんと行い、必要な時期に適切な修繕を行うことで長持ちさせる
ことができるわけです。逆に維持管理をおろそかにすれば、資産としての価値が落ちてしまいますし、実質的な
寿命を短くしてしまいます。つまり「マンションの現実的な寿命は、そのマンションの入居者と管理会社が
作り上げるもの」とも言えるのではないでしょうか。
「いつ寿命が来るのか」とか「古くなると売れなくなるのではないか」という心配もあるかもしれません。
しかし、ヴィンテージマンションのように、築30~40年たっても資産価値を保ち、売買の取引が行われている
ケースは珍しくないのです。建物自体も朽廃するどころか、むしろ重厚さを増し、魅力を高めています。
これまで説明してきたように、「マンションの寿命」には、物理的な寿命、機能的な寿命、経済的な寿命、
社会的な寿命のように、さまざまな側面があり、相互に絡み合っています。
個々のマンションが置かれた環境や維持管理の仕方によっても、寿命は変わってきます。
単なる数字にこだわるのではなく、どれだけ愛着を持って住み続けられるか、という視点にたって、
総合的に判断するのが良いのではないでしょうか。
(AllAbout マンションの資産価値より)
 大分の中古住宅・土地・マンションなど不動産を「買う」「売る」ならお気軽にご相談ください!
大分の不動産「売りたい買いたいネット」
中古売家、新築売家、中古マンション、売土地もご紹介やご売却、各種減税・優遇金利・補助金のご相談もお任せ下さい。
http://www.uritai-kaitai.net/
大分の中古住宅・土地・マンションなど不動産を「買う」「売る」ならお気軽にご相談ください!
大分の不動産「売りたい買いたいネット」
中古売家、新築売家、中古マンション、売土地もご紹介やご売却、各種減税・優遇金利・補助金のご相談もお任せ下さい。
http://www.uritai-kaitai.net/Posted by 売りたい買いたいネット at 10:52│Comments(0)
│不動産のイロハ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。





